はじめに
最近、SDGs、地球温暖化、脱炭素、カーボンニュートラル(CN)など環境問題を取り上げたワードを耳にすることが多いと思います。
今日の日本では「環境基本法(1993年制定)」のもとに、環境問題に取り組む様々な法律が整備されています。今回は、日本における法の制定と公害問題、環境問題がどのように関わってきたのか、その歴史を学んでいきましょう。
公害問題のはじまり
(明治時代から昭和初期)
日本で環境関連の法律が制定されることになったのは、「公害問題」が広く社会全般の問題となった昭和30年代後半、日本経済が高度経済成長期を迎えた頃でした。
しかし、それまでの、明治時代から昭和初期にかけても公害は発生していました。明治維新後、欧米の列強に追いつこうと、富国強兵を目指した殖産興業により、急速な近代化と工業化を進める中で「公害」が発生しました。その中で特に有名なのが、明治時代初期に栃木県と群馬県の渡良瀬川周辺で起きた「足尾銅山鉱毒事件」です。日本で最初の公害事件であり、「公害の原点」と言われています。
足尾銅山での銅製錬による多量の銅化合物や硫酸などが渡良瀬川へ流出したことにより、流域の農民や漁民は、鉱毒による多大な被害を受け、人の健康にまで被害が及びました。
明治時代から昭和初期には、足尾銅山の鉱毒事件を始め、愛媛県の別子銅山や茨城県の日立鉱山における煙害、そして、東京・大阪などの都市部での工場立地による局地的な大気汚染や水質汚濁などが発生しました。
しかし、残念なことに、当時の社会情勢のもとでは、人々の人権は今日のように尊重されず、深刻な社会問題として認識されませんでした。

明治時代は、急速な近代化が進み、さまざまな産業が発展した反面、「公害」をもたらす結果となってしまったんだね。特に鉱山開発による公害が代表的で、文字通り「鉱害」だったんだね。
高度経済成長期と四大公害事件
(昭和30~40年代)
昭和30年代後半、日本が高度経済成長期を迎えると、公害が深刻な社会問題となり、大気汚染をはじめ、水質汚濁、自然破壊、騒音・振動などの問題が日本各地で顕在化し、深刻度を増していきました。中でも、公害により住民へ大きな被害をもたらした代表的な4つの公害を四大公害事件といい、それに伴う症状を四大公害病と呼んでいます。
四大公害病

四大公害病のうち、水俣病、新潟水俣病、イタイイタイ病は、水域の重金属汚染問題であり、四日市ぜんそくは大気汚染問題です。化学工場の排水・排ガス処理の不十分さに起因しているこれらの公害は、産業型の公害と呼ばれ、地域住民の命や健康に深刻な被害をもたらしました。
このように各地で公害問題が発生した結果、公害対策を望む世論が急激に高まっていき、対象とする公害の範囲、国、地方公共団体および事業者の責務の明確化など、施策推進の基本原則を明らかにするべきであるとの声も高まりました。

日本では、戦後の高度経済成長期に、経済の発展と引き換えに、環境汚染が拡大していき、公害が大きな社会問題となったんだ。しかし、企業の利益を優先させてしまった結果、原因追究や対策が遅れてしまったんだ。被害者による訴訟や裁判を経て、ようやく、厳しく企業の責任が問われることになったんだね。
公害対策への取り組みと公害対策基本法の制定
日本では、四大公害事件に代表される環境汚染の危機的状況から抜け出すことが最初の目標となり、1967年に「公害対策基本法」が制定されました。この法律は、1960年代の各地での産業活動に起因する公害問題の発生に対し、事業者が発生させた汚染物質などの規制を主眼としていました。当時起きた公害の防止が目標とされ、これに基づき大気や水質、騒音などの環境基準が設けられ、工場や事業所からの排ガスや排水の規制がなされました。
1960年代の末から1970年代のはじめにかけては、経済先進諸国のなかで、環境問題が共通の問題となっていた時代であり、日本でも、1970年11月25日に召集された臨時国会は公害国会といわれ、公害・環境関連の14法案が国会を通過しました。「水質汚濁防止法」もこのときの国会で法案が可決されました。そして、1971年には環境庁が発足し、環境行政の基本的な体制ができ上がり、環境問題解決への本格的な取り組みがはじまりました。また、公害防止とともに自然環境一般を保全するために、「自然環境保全法」が1972年に制定されました。
- 1950年代後半~1970年代
「高度経済成長期」
産業型の公害による健康被害 - 国民世論の急激な高まり
「産業発展のためとはいえ、
公害は絶対に許せない」 - 公害対策に関する施策が
総合的に進められることの
必要性 - 1967年(昭和42年)
公害対策基本法の制定 - 1971年(昭和46年)
環境庁の発足

国民世論の高まりによって、ようやく公害対策に関する施策が総合的に進められることとなったんだね。まずは、当時発生したような公害を防止することが、最初の目標とされたんだね。このように、四大公害病が起こった結果、ようやく公害対策に関する施策が総合的に進められることになったんだよ。
都市型・生活型公害の拡大
(1970年代)
1967年に「公害対策基本法」が制定されたことにより、1970年代には、公害対策に関する法律が整備され、公害防止のための規制が行われていった結果、水銀などの人の健康に係る有害な物質による水質汚濁の状況は著しく改善しました。
しかし、高度経済成長によって、大量生産、大量流通、大量消費、大量廃棄の結果、産業活動だけではなく、人々の日常の生活行動が大きな原因となって公害が発生するようになりました。
自動車利用による排ガスは、窒素酸化物による大気汚染をもたらしました。
また、河川や湖沼、海域などの有機汚濁は、工場排水や、農業、養殖漁業などからの排水だけでなく、家庭からの生活排水も原因となりました。1970年代後半に琵琶湖に発生した赤潮の主な原因は富栄養化で、生活排水中の合成洗剤に含まれるリンにも注目が集まりました。
さらに、大量廃棄が行われた結果、廃棄物処理が大きな問題となっていきました。
こうした変化により、従来の環境行政の枠組みでは対応できない状況になっていきました。

近年の公害問題は、産業型公害から、人々の日常の生活行動が大きな原因となって発生する都市型・生活型公害へと問題構造が変化していったんだね。
地球環境問題と環境基本法の制定
(1980年~1990年代)
1980年代後半からは、世界的に、地球温暖化やオゾン層の破壊、酸性雨、熱帯林の減少、砂漠化、種の絶滅、海洋汚染、有害廃棄物の越境問題、さらに開発途上国での環境汚染問題など、地球環境問題が注目されるようになっていきました。
このような中で、1992年にブラジルのリオデジャネイロで、地球サミットが開かれました。この地球サミットの正式名称は、環境と開発に関する国連会議(UNCED:United Nations Conference on Environment and Development )であり、約180カ国の政府や国際機関が参加した、環境保全と持続可能な開発に焦点を当てた国連会議でした。「持続可能な開発」とは、人類の将来世代にわたる持続的な生存を可能とする開発のことです。この会議により、「持続可能な開発」に向けての国際合意を示す各種の文書が採択されました。
このような世界的な動向と、また近年の公害問題が、都市型・生活型公害となっており、産業活動だけでなく、人々の日常生活行動が大きな原因となって発生する問題も多くなってきたことから、それまであった「公害対策基本法」では、複雑化・地球規模化する環境問題に対応できなくなっていきました。環境問題の性質の変化に応えるため、1993年に「環境基本法」が新たに制定されました。
この環境基本法の制定により、従来の公害対策基本法は廃止され、自然環境保全法も環境基本法に沿って改正され、総合的に環境問題の解決に取り組むこととなりました。
- 1980年代
環境問題のグローバル化 - 複雑化・地球規模化する環境問題に
対応できなくなってくる - 1992年(平成4年)
ブラジルのリオデジャネイロで
地球サミット開催
「環境と開発に関する宣言」を
はじめとする5つの条約・宣言の採択 - 1993年(平成5年)
「環境基本法」の制定 - 2001年(平成13年)
環境省の発足

一口に環境問題といっても、環境問題の概念は時代により変化していき、環境問題の範囲も、より広域となっていったんだ。そのため「環境基本法」によって、総合的に環境問題に取り組むことになったんだね。
環境関連法規の制定とその年表
ここで、環境関連法規の制定と、環境をめぐる動きを年表で振り返ってみましょう。
| 年 | 環境をめぐる動き | 環境関連法規の制定 |
|---|---|---|
| 1878(明治11年)頃 | 渡良瀬川(栃木県)で 足尾銅山の鉱毒被害が著しくなる |
|
| 1956(昭和31年) | 水俣病公式確認 (チッソ付属病院が水俣保健所に 患者の発生を報告) |
|
| 1958(昭和33年) | 「工場排水等の規制に関する法律」公布 「公共用水域の水質の保全に関する法律」公布 「下水道法」公布 |
|
| 1961(昭和36年) | 四日市ぜんそく患者多発 | |
| 1964(昭和39年) | 厚生省環境衛生局に公害課設置 | |
| 1965(昭和40年) | 新潟水俣病を公式確認 | 「公害防止事業団法」公布 |
| 1967(昭和42年) | 「公害対策基本法」公布 | |
| 1968(昭和43年) | 厚生省、イタイイタイ病は 公害との見解を発表 |
「大気汚染防止法」公布 「騒音規制法」公布 |
| 1969(昭和44年) | 初の「公害白書」発表 | 「公害に係る健康被害の 救済に関する特別措置法」公布 |
| 1970(昭和45年) | 「公害国会」召集 公害関係14法制定、 「公害防止に関する決議」を議決 |
「公害防止事業費事業者負担法」公布 「水質汚濁防止法」公布 「人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律」公布 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」公布 「農地用の土壌の汚染防止等に関する法律」公布 「海洋汚染防止法」公布 |
| 1971(昭和46年) | 環境庁発足 | 「悪臭防止法」公布 「特定工場における公害防止組織の 整備に関する法律」公布 |
| 1972(昭和47年) | 初の「環境白書」発表 | 「自然環境保全法」公布 |
| 1973(昭和48年) | 「瀬戸内海環境保全臨時措置法」公布 「公害健康被害補償法」公布 |
|
| 1979(昭和54年) | 滋賀県が 「琵琶湖富栄養化防止条例」制定 |
|
| 1980(昭和55年) | 環境庁、 「富栄養化対策について」を発表、 各省庁に対し燐を含む合成洗剤の 使用自粛等に関して要請 第一次水質総量規制がスタート |
|
| 1982(昭和57年) | 湖沼の窒素・リン環境基準を告示 | |
| 1983(昭和58年) | 「浄化槽法」公布 | |
| 1984(昭和59年) | 「湖沼水質保全特別措置法」公布 | |
| 1988(昭和63年) | 「特定物質の規制等による オゾン層の保護に関する法律」公布 |
|
| 1991(平成3年) | 「再生資源の利用の促進に関する法律」公布 | |
| 1992(平成4年) | 地球サミット (環境と開発に関する国連会議) |
「自動車から排出される 窒素酸化物の特定地域における 総量の削減等に関する特別措置法 (通称:自動車NOx法)」公布 |
| 1993(平成5年) | 「環境基本法」公布 | |
| 1997(平成9年) | 「環境影響評価法」公布 | |
| 1998(平成10年) | 「地球温暖化対策の推進に関する法律」公布 | |
| 1999(平成11年) | 「ダイオキシン類対策特別措置法」公布 | |
| 2000(平成12年) | 「循環型社会形成推進基本法」公布 | |
| 2001(平成13年) | 環境省発足 | 「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の 適正な処理の推進に関する特別措置法 (通称:PCB特措法)」公布 「特定製品に係るフロン類の回収 及び破壊の実施の確保等に関する法律 (通称:フロン回収・破壊法)」公布 |
| 2002(平成14年) | 「土壌汚染対策法」公布 | |
| 2003(平成15年) | 「特定産業廃棄物に起因する 支障の除去等に関する特別措置法」公布 「環境の保全のための意欲の増進 及び環境教育の推進に関する法律」公布 |
|
| 2004(平成16年) | 「環境情報の提供の促進等による 特定事業者等の環境に配慮した 事業活動の促進に関する法律」公布 |
|
| 2005(平成17年) | 「特定特殊自動車排出ガスの 規制等に関する法律」公布 |
|
| 2006(平成18年) | 「石綿による健康被害の救済に関する法律」公布 | |
| 2007(平成19年) | 政府、初の 「環境・循環型社会白書」発表 |
「国等における温室効果ガス等の 排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律 (通称:環境配慮契約法)」公布 |
| 2008(平成20年) | 「生物多様性基本法」公布 | |
| 2009(平成21年) | 初の「環境・循環型社会・ 生物多様性白書」発表 |
「水俣病被害者の救済 及び水俣病問題の解決に関する特別措置法 (水俣病特措法)」公布 |
| 2013(平成25年) | 「放射性物質による環境の汚染の防止のための 関係法律の整備に関する法律」公布 |
|
| 2015(平成27年) | 「水銀による環境の汚染の防止に関する法律」公布 |
※この表は、環境省 五十年史 資料編一覧 Ⅰ環境と社会の五十年(年表)資料編pp.1~34より引用して作成
環境関連法規は、「環境基本法」の基本理念を実現させるために、環境問題に取り組む時代のニーズに応じて、多岐にわたる個別法の新たな制定および改正が行われています。「環境基本法」の下位法として、2000年には「循環型社会形成推進基本法」が、2008年には「生物多様性基本法」が制定されました。それに伴い、環境関連の法整備が進められています。

三進製作所は、水処理を通して、環境への負荷の低減や資源循環型社会の構築に貢献しているよ。
【参考文献】
- 1)早川豊彦,種茂豊一 他; 環境工学の基礎, 地球環境とその保全, 実教出版, pp.70~83
- 2)環境省五十年史(資料編)Ⅰ 環境と社会の五十年(年表)
- 3)公害等調整委員会事務局総務課企画法規係; 「明治150年」関連施策 明治の公害と公害紛争処理制度について
- 4)南川秀樹; 明治、大正から公害国会(1970年)以前の環境行政の動向と法制度(その1)―廃棄物対策を中心に―, 環境技術会誌, 181号(2020)
- 5)昭和44年版公害白書
- 6)平成5年版環境白書
- 7)平成6年版環境白書





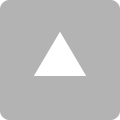
環境関連法規制定のきっかけは、「公害問題」だったんだよ。しかし、次第に部分的、局所的な公害問題にとどまらず、地球規模での「環境問題」が取り上げられるようになったんだ。